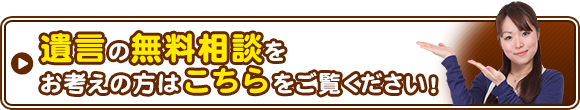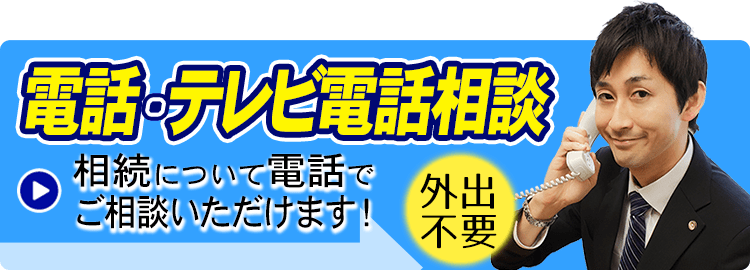遺言の開封方法についてのQ&A
封がしてある遺言書は自分で開封してもよいのですか?
封がしてある自筆証書遺言(法務局で保管されているものを除く)や秘密証書遺言は、ご自身で開封してはいけません。
正確には、家庭裁判所における検認の手続きの際に、相続人またはその代理人の立会いのもとでなければ開封することができない旨、法律で定められています。
【参考条文】(民法)
(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
参考リンク:e-gov法令検索(民法)
なお、法務局における自筆証書遺言保管制度をご利用の場合には、自筆証書遺言に封をすることはできません。
検認の手続きはどのようにすればよいのですか?
封がしてある自筆証書遺言と秘密証書遺言は、家庭裁判所での検認の手続きの際に開封します。
検認の申立てをする際は、基本的には検認の申立書、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本を用意し、これらを管轄の家庭裁判所に提出する必要があります。
もし代襲相続が発生している場合には、被代襲者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。
相続関係によっては、これら以外にも必要となる戸籍謄本もあります。
検認の申立てがあった後、家庭裁判所は相続人に対して検認期日(家庭裁判所において遺言の検認が行われる日時)の通知をします。
検認期日当日には、封がしてある遺言を家庭裁判所に提出します。
そして、家庭裁判所で遺言の開封をし、遺言の内容を確認したうえで遺言書の検認が行われます。
参考リンク:裁判所・遺言書の検認
相続税にも強い弁護士に相談すべき理由は何ですか? Q&Aトップへ戻る